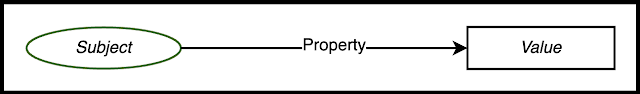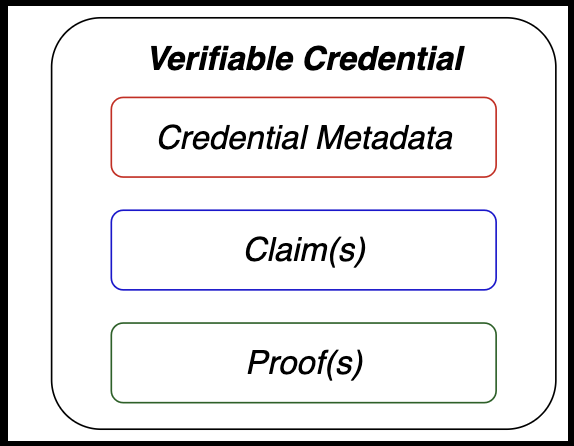引き続きW3C Verifiable Credentials Overviewを見ていきます。
前回触れた通り、以下の目次構成となっているドキュメントです。
- Introduction
- Ecosystem Overview
- Verifiable Credentials Data Model
- Securing Credentials
- Bitstring Status List
- Additional Publications
今回はIntroductionを見ていきます。
まずは本文書の目的から。詳細ではなく概念を把握してもらうことが主目的です。
(なお、全体を通じて日本語訳はDeepLを使った機械翻訳です)
This document provides a non-normative, high-level overview for W3C's Verifiable Credential specifications and serves as a roadmap for the documents that define, describe, and secure these credentials. It is not the goal of this document to be very precise, nor does this overview cover all the details. The intention is to provide users, implementers, or anyone interested in the subject, a general understanding of the concepts and how the various documents, published by the Verifiable Credentials Working Group, fit together.
この文書は、W3Cの検証可能な資格証明書の仕様に関する非規範的な概要を提示し、これらの資格証明書を定義、説明、保護する文書のロードマップとしての役割を果たします。この文書は、非常に正確であることを目指しているわけではなく、またこの概要はすべての詳細を網羅しているわけでもありません。このドキュメントの目的は、ユーザー、実装者、またはこのテーマに関心のある人々に、概念の一般的な理解と、検証可能な資格情報ワーキンググループが発行するさまざまなドキュメントがどのように関連しているかを理解してもらうことです。
1.1 High Level View of the Specifications
Figure 1 provides an overview of the main building blocks for Verifiable Credentials, including their (normative) dependencies. For more details, see the subsequent sections in this document.
図 1 は、検証可能な資格情報の主な構成要素の概要を示しており、それらの(規範的な)依存関係も含まれています。 詳細については、このドキュメントの以降のセクションを参照してください。
先に図1を貼っておきます。Verifiable Credential Data Modelばかりに目が行きますが様々な関連スペックから構成されていることがわかります。
 |
| 図1 Verifiable Credentials Working Group Recommendations |
The Verifiable Credentials Data Model v2.0 [VC-DATA-MODEL-2.0] specification, which defines the core concepts that all other specifications depend on, plays a central role. The model is defined in abstract terms, and applications express their specific credentials using a serialization of the data model. The current specifications mostly use a JSON serialization; the community may develop other serializations in the future.
他のすべての仕様が依存するコア概念を定義する Verifiable Credentials Data Model v2.0 [VC-DATA-MODEL-2.0] 仕様が、中心的な役割を果たします。このモデルは抽象的な用語で定義され、アプリケーションはデータモデルのシリアライズを使用して固有のクレデンシャルを表現します。現在の仕様では、主に JSON シリアライズが使用されていますが、将来的にコミュニティが他のシリアライズを開発する可能性もあります。
シリアライズ周りはVCDM2.0で明確に変化した部分ですね。
ここからは各構成要素の役割を紹介しています。
まずはVC-JSON-SCHEMAはクレデンシャルの解釈を行うためのスキーマを定義しています。
When Verifiable Credentials are serialized in JSON, it is important to trust that the structure of a Credential may be interpreted in a consistent manner by all participants in the verifiable credential ecosystem. The Verifiable Credentials JSON Schema Specification [VC-JSON-SCHEMA] defines how [JSON-SCHEMA] can be used for that purpose.
検証可能なクレデンシャルを JSON でシリアライズする場合、検証可能なクレデンシャルエコシステムに参加するすべての関係者が、クレデンシャルの構造を一貫性のある方法で解釈できると信頼することが重要です。検証可能なクレデンシャルの JSON スキーマ仕様書 [VC-JSON-SCHEMA] では、[JSON-SCHEMA] をその目的で使用する方法を定義しています。
クレデンシャルを保護するメカニズムについて触れていきます。
Credentials can be secured using two different mechanisms: enveloping proofs or embedded proofs. In both cases, a proof cryptographically secures a Credential (for example, using digital signatures). In the enveloping case, the proof wraps around the Credential, whereas embedded proofs are included in the serialization, alongside the Credential itself.
クレデンシャルは、2つの異なるメカニズム(エンベロープ型証明または埋め込み型証明)を使用して保護することができます。いずれの場合も、証明は暗号技術を使用してクレデンシャルを保護します(例えば、デジタル署名を使用)。エンベロープ型の場合、証明はクレデンシャルを包み込みますが、埋め込み型の場合は、クレデンシャル自体とともにシリアル化に含まれます。
エンベロープ型、いわゆるJWSは全体を署名してしまう方式です。
A family of enveloping proofs is defined in the Securing Verifiable Credentials using JOSE and COSE [VC-JOSE-COSE] document, relying on technologies defined by the IETF. Other types of enveloping proofs may be specified by the community.
JOSE および COSE を使用した検証可能なクレデンシャルの保護 [VC-JOSE-COSE] 文書では、IETF が定義した技術に依存する、エンベロープ型証明の一連が定義されています。その他のエンベロープ型証明は、コミュニティによって指定される場合があります。
埋め込み型はVC Data Integrityの話ですね。
The general structure for embedded proofs is defined in a separate Verifiable Credential Data Integrity 1.0 [VC-DATA-INTEGRITY] specification. Furthermore, the Working Group also specifies some instances of this general structure in the form of the "cryptosuites": Data Integrity EdDSA Cryptosuites v1.0 [VC-DI-EDDSA], Data Integrity ECDSA Cryptosuites v1.0 [VC-DI-ECDSA], and Data Integrity BBS Cryptosuites v1.0 [VC-DI-BBS]. Other cryptosuites may be specified by the community.
埋め込み証明書の一般的な構造は、別個の検証可能なクレデンシャルデータ完全性 1.0 [VC-DATA-INTEGRITY] 仕様で定義されています。さらに、ワーキンググループは、この一般的な構造を「暗号スイート」の形でいくつか規定しています。データ完全性 EdDSA 暗号スイート v1.0 [VC-DI-EDDSA]、データ完全性 ECDSA 暗号スイート v1.0 [VC-DI-ECDSA]、データ完全性 BBS 暗号スイート v1.0 [VC-DI-BBS]。コミュニティによって他の暗号スイートが指定される場合もあります。
そして発行済みクレデンシャルのステータス(取り消し状態)を管理するためのBitString Status Listです。以前StatusList2021とか言っていたものですね。(過去の記事)
相変わらずBitStringです。。。
The Bitstring Status List v1.0 [VC-BITSTRING-STATUS-LIST] specification defines a privacy-preserving, space-efficient, and high-performance mechanism for publishing status information, such as suspension or revocation of Verifiable Credentials, through the use of bitstrings.
Bitstring Status List v1.0 [VC-BITSTRING-STATUS-LIST] 仕様は、検証可能なクレデンシャルの一時停止や取り消しなどのステータス情報を、ビットストリングを使用して公開するための、プライバシー保護、省スペース、高性能なメカニズムを定義しています。
そして最後はコントローラードキュメントです。DIDにおけるDID Documentなどクレデンシャルを検証するための方法などについて書かれているものです。
Finally, the Controller Documents 1.0 [CONTROLLER-DOCUMENT] specification defines some common terms (e.g., verification relationships and methods) that are used not only by other Verifiable Credential specifications, but also other Recommendations such as Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 [DID-CORE].
最後に、Controller Documents 1.0 [CONTROLLER-DOCUMENT] 仕様では、他の検証可能な資格情報仕様だけでなく、分散型識別子 (DID) v1.0 [DID-CORE] などの他の勧告でも使用されるいくつかの共通用語(検証関係や方法など)を定義しています。
とりあえずはIntrodutionなので全体の概要が語られましたが、実際問題この関係性についてはちゃんと理解しておかないと後からついていけなくなるので非常に大切なパートでした。
次回はEcosystem Overviewを見ていきます。